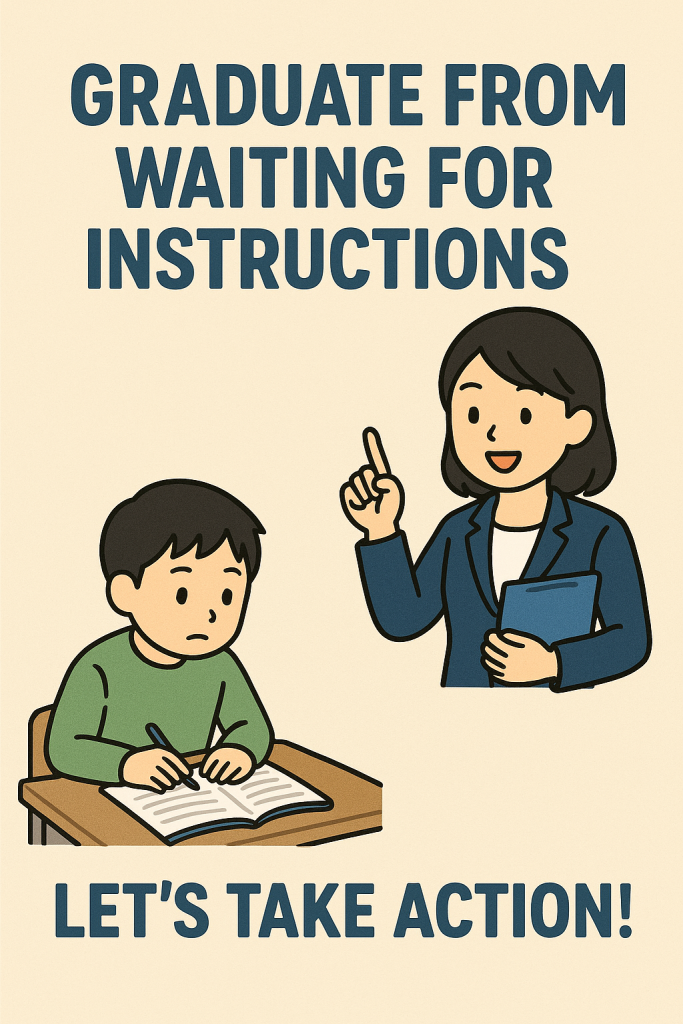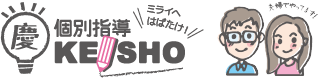突然ですが、社会でよく聞く「指示待ち」という言葉、皆さんはどう感じますか?
会社で「指示待ち社員」の問題が取り沙汰されることがありますが、これは誰かの指示がなければ、自分で「何をすべきか」「どうすればいいか」を考え、判断し、行動できないことが大きな原因です。この問題は、私たちの「学習」にも深く関係していると思います。
教育界でも、かつての知識の詰め込み教育から、「思考力・判断力・表現力」を重視する現在の学習指導要領へと改定されました。これは、社会が求める人材の変化を反映していると言えます。しかし、現場で生徒たちと向き合っていると、まだまだ「指示待ち」の姿勢を感じることが少なくありません。
「この問題の後は何をすればいいんだろう…」「先生が来るまで待っていよう」といった生徒の姿を見るたびに、私自身も「分かっているなら遠慮せずにどんどん進めてほしい!」「分からなければすぐに聞いてくれたらいいのに!」と、もどかしく思うことがあります。
なぜ、そうなるのでしょうか?もちろんシャイな性格や生徒の特性などもありますが、それは、「間違えることへの抵抗感」や、「自分で判断するトレーニングの機会が少ない」という今の日本の教育の風潮が影響しているのかもしれません。
☆間違いからこそ成長する
だからこそ、当塾では、生徒たちに「指示待ち」から「主体的な学習者」へと変わってもらうことをとても大切にしています。私たちは、勉強の内容はもちろん、些細なことからでも「自分で判断する(考える、決める)」機会を意図的に提供するように心がけています。
「どの問題を次に解くか」「今日の目標をどこに設定するか」—小さなことでも、自分で考えて、決める経験を日々積み重ねることが、未来の大きな選択につながると私は信じています。
人間は、間違いから最も多くを学び、成長するものです。また、間違えたら修正して、次に同じミスをしなければいいんです。私自身、若かりし頃は数えきれない失敗を経験し、周りの人に助けられながら成長させてもらいました。
☆「どんといってみよう!」
皆さんの挑戦は、決して一人ではありません。私たち講師陣も含め、きっと周りには皆さんを信じて応援してくれる「応援団」がいるはずです。
私たちと一緒に、自分で考え、決める力を身につけていきましょう!